コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」
2023年4月 6日ファンダメンタル分析とテクニカル分析
 大阪ネットサポートセンター 高橋
大阪ネットサポートセンター 高橋
-
私が入社した1986年(昭和61年)は、バブル突入の年とも言われるたいへん賑やかな時代でした。
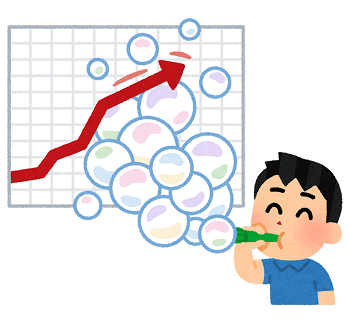
オフィスの中は株価を表示するテレビが何十台とあり、何百銘柄の値段が表示されていました。
また、直接取引所の場立ちと繋がっている"場電"が支店の真ん中にありました。
場電で注文を出す時は大声を出すのでまるで中央卸売市場のセリのような雰囲気。
その雰囲気の中、多くの先輩はお客様に対して相場を語っていました。
「今後、こんな時代が来るので、こういう企業が潤っていくだろう」と、いわゆる「風が吹けば桶屋が儲かる」方式での見方です。
我々若輩が先輩に相場のことを聞くと、いつも「10年早い」とか「相場は相場に聞け」と言われたものですが、私の同期生が「相場は物言いません」と真顔で答え、別室に呼ばれコンコンと怒鳴りつけられていたことをよく覚えています。
この時代は、買えば上がる時代でもあり、ほとんどの先輩は中長期の相場(いわゆるファンダメンタル分析)を見ていました。「ローソク足」を毎日書いていた先輩はおられましたがその先輩くらいでしたし、「酒田五法」もありましたが「仕手株」が好きだった先輩たちが少し利用していたぐらい。現代では当たり前の「テクニカル分析」というものはあまりなかったような気がします。1991年、バブルは崩壊し、時代は進んだ21世紀初頭のITバブルも崩壊したころ、一部の先輩たちではありましたが本格的なテクニカル分析を堂々と語る方々が現れ始めました。
そのころにはテクニカル分析を中心としたファンドマネージャーが出てきたり、テクニカル分析を中心としたセミナーもたくさん増えました。
バブルの時は自分の買った銘柄が少々下がっても、塩漬け(その後の塩漬けとは期間は比べ物にならないので後から思えば浅漬け?)にしておけばすぐもとにもどりましたが、時代とともにそれは難しいことがわかってきました。
結局、「失われた10年」で、中長期で持ってもなかなか運用益が出ないという時代に突入したのだと思います。短期の運用で「ロスカット」しながら年間単位で運用益を出していくファンドマネージャーも増えてきました。現在は「デイトレ」とか言って個人投資家の運用も主流となってきています。
その後、アベノミクスがスタートするまで「失われた20年」、マーケットではリーマンショック、コロナショックなどいろいろなことが起こりましたが、どんなにいい方式のテクニカル分析が出てきても「間違ったら、すぐに方向転換をする」「スパッと割り切って新しい方へ素早く動くことが後々にはいい結果が出る」という先輩の言葉通り、「間違ったら、早めに方向転換」。それは今も昔も変わらないと思います。(豆知識:バブルとは、1986年から1991年2月までの期間を言われます。1985年のプラザ合意により1ドル250円だった為替は1年後には150円に。急激な円高により当時の日本のGDPの高い比率を占める製造業は大打撃を受け、政府は内需主導型の経済成長を促すために公共投資の拡大などの積極財政を、日銀は公定歩合を引き下げ、長期金融緩和状態となり景気も拡大したが、土地や株式などへの投機でバブル発生となったとされます。)









