コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」
2024年3月27日画像生成AIと著作権
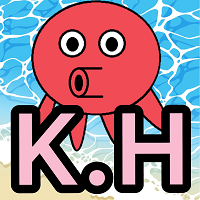 大阪ネットサポートセンター 堀池
大阪ネットサポートセンター 堀池
日頃は格別のご愛顧いただき、ありがとうございます。
大阪ネットサポートセンターの堀池です。
近頃はエヌビディア(米国/NVDA)を筆頭とした「生成AI」ブームで、相場では半導体銘柄が注目を集めています。
国内株では、東京エレクトロン(日本/8035)やアドバンテスト(日本/6857)、子会社のARM(米国/ARM)の株価上昇で株価が上昇したソフトバンクG(日本/9984)なども株価が大きく上昇しており、34年ぶりの日経平均の史上最高値更新には半導体銘柄の多大な貢献がありました。
生成AIへの需要は、かつてスマートフォンへの需要増が半導体需要を増加させたレベルの話とは全く違います。企業がコスト低減による生産性向上につなげるため積極投資を行っているからです。生成AIへの投資は、消費者向けの需要拡大期待にあるのではなく、事業向けの需要がけん引していることから、この相場はまだまだ続くと思われます。
AIという言葉の定義が曖昧な中で、従来のAIは、学習済みのデータの中から適切な回答を提示する性質を持つものでしたが、生成AIはゼロからイチを生み出す性質をもっています。今の相場は、この「何かを作りだすAI」=「生成AI」に注目が集まっています。
「生成AI」の技術は、テキストや画像の他、音楽を作曲したり、数分程度の短い動画すら生成できるまでに向上しました。しかし、今まで人類が持ち得なかった技術なので、法律が間に合っていない現実もあります。
今回は、生成AIの①画像生成と②著作権についてお話したいと思います。
最初に、①画像生成についてお話します。
生成AIの機能のひとつである画像生成をするには、文章を入力します。細かい注文や設定、画像の雰囲気やサイズなど細かな指定も可能なものが多く、指定に沿った画像を作ってくれます。
そもそも「生成AIって何?」という方にも、生成AIのイメージが湧きやすいように、今回は、PDFリーダーでお馴染みのアドビ社(米国/ADBE)のAI画像生成ツール「Adobe Firefly」を使って例示してみます。
「日本の証券会社の営業マン、スーツを着ており、オールバック、笑顔、眼鏡をかけている」と入力して、生成された画像がコチラ。
なんとなくいそうな人が出てきましたね。
イメージに合う人を探してモデルになってもらい、写真を撮ってとなると大変ですが、この写真はAIが作り上げたもの。
しかし、私には、どことなく現実的ではないと申しますか、光の当たり方などが不自然に感じ、「AIっぽさ」のある画像に見えます。
条件を加えてみましょう。
「日本の証券会社の営業マン、スーツを着ており、オールバック、笑顔、眼鏡をかけている、年齢は50代」
と入力して生成された画像はコチラ。
これはかなり自然ではないですか?
この人もAIが作り出したもので実在はしませんが、この画像が会社のHPに社員紹介として載っていてもAIと見抜ける人はなかなかいないと思います。
ただ、よく見るとネクタイの部分などは、画像が崩れています。
更に条件を加え、これをアニメ風にしようと思います。
「日本の証券会社の営業マン、スーツを着ており、オールバック、笑顔、眼鏡をかけている、年齢は50代、アニメ風」

こんな風に文章を入れるだけで、絵心のない私でも簡単に注文通りのイラストを手に入れることができました。
これをイラストレーターの方に依頼すれば当然費用が発生しますし、納期までの時間を待つ必要があります。あるいはイメージと違うイラストが納品された場合、手直しを依頼するか悩むことになります。
AIであれば費用は無料、もしくは無料に近いコストになりますし、ほんの数十秒で納品され、また大量の候補を出力してその中から選ぶことも可能です。
企業としては、生み出す能力が無い社員の代わりに使えることとなり、また様々なコストを抑えることができるというわけです。
しかし、これらには議論されるべき問題が残されています。
それが今回のタイトルにもある著作権についてです。
②次に、生成AIの著作権についてお話します。
最初の画像の二人は、実在する人間ではありません。
あるいは後半のイラストは今回、AIが私の注文を受けて作ってくれた世界でたった1枚のイラストです。
ただ最初の画像の二人は「実在する誰かの写真」を大量に学習した上で作成された画像で、
後半の2枚のイラストは「誰かの作品」を大量に学習した上で作成されています。
今回はお見せすることができませんが、「有名な漫画家の○○さんの画風で描いて欲しい」などと注文することも可能ですし、あるいは気に入ったイラストレーターの過去の作品を学習させその人の画風のイラストを手に入れることもできます。(今回使用したAdobe FireflyはAIの学習の過程にするデータの透明性を実現する活動にも取り組んでおり、商用利用が可能となっています)
ここで現行の法、あるいは法運用では対処できない問題が出てきます。
例えば私がイラストを勉強し、気に入ったイラストレーターの画風を手に入れるために大量に模写等の練習をし、努力して自分で描けるようになったらどうでしょうか?
これは私の著作権として認められるようになります。
一方でAIでの学習においては、私は特に努力をすることなく、その人のイラストをAIに読みこませるだけで簡単に画風を盗むことができてしまいます。
どこまでが著作権の侵害でどこからがセーフなのか不明確なのです。
今後、著作権の侵害のラインが明確に定められたとしても、AIの生成物が著作権の侵害に当たるという証明は難しいのかも知れません。
日本の文化庁はAIと著作権について「学習」「生成・利用」「生成物が著作物になるか」、それぞれを段階にわけて考えることが重要であるとしています。
「学習」においては「著作権者の利益を不当に害する場合」を除いて許諾なく可能、
「生成・利用」においては非AI生成物と同様に著作権侵害かどうか判断される、
「著作物になるかどうか」については「創作意図」と「創作的寄与」の有無によって変わるとしているようです。
仮に商業的なイラストをAIのみが作成するようになるとAIの作成物をAIが学習するようになり、最終的に新しいものが生まれなくなるような懸念もあるようです。
今後、AIによって複雑化した法的な問題は多方面にも発生する可能性があります。
少し前までは「クリエイティブな仕事以外はAIにどんどん奪われていく」なんて言われていたのですが、皮肉なことにクリエイティブなジャンルの仕事が先行して奪われています。
個人的にはそこに「正確性」が求められないが故にクリエイティブな領域での利用が先行しているのではないかと考えています。AIが人間と同等かそれ以上の信頼性を得た時に、人類社会がどのように変化するのか、楽しみである反面、不安も感じます。
当面継続しそうなテーマである生成AI。
関連銘柄は、私共のログイン後のマーケット情報→キーワード検索で「生成AI」と入力すると、検索できます。









